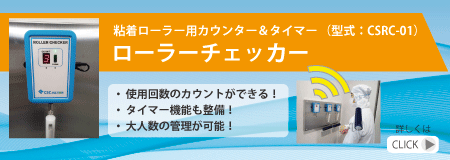|
| 【実験①】 アースの効果 |
 |
【実験の準備】
- アース線(ワニグチクリップ付き)、導電性マット
- チャージプレートモニター(プレートの上に0~5KVの正負の電気を発生させることができ、また、発生した静電気が減衰する時間(秒)を測定することができる装置)
静電気対策の方法のひとつとして表面抵抗値が導電性レベルのものを使用するという方法があります。導電性ゴムマットなどが代表的な製品となります。しかし、導電性製品もアースをしなければ、静電気を逃がすことはできません。 |
 実験ムービー 実験ムービー
|
 静電気対策のポイント 静電気対策のポイント
アースにつなぐことは静電気対策の基本中の基本ですが、アースが途切れていれば何の意味もありません。導電性マットもアースにつながなければただのマットです。 |
  |
 |
| 【実験②】 アースでは静電気は防ぐことはできない |
| しかし、アースは万能というわけではありません。絶縁物が帯電するとそもそも電気が流れないわけですから、アースにつないでも静電気の除去はできません。 |
 実験ムービー 実験ムービー
|
 静電気対策のポイント 静電気対策のポイント
絶縁物の帯電はアースでは除去することができません。
空気中に浮かぶホコリが帯電している場合も同様ですから、ホコリの静電気付着を防ぐには、イオナイザーによる静電気の除去、もしくは、そもそも、ホコリの少ない空間(クリーン化)にする必要があります。 |
 |
| 【実験③】 空気の帯電と除去方法 |
| 静電対策がされていないエア配管から出るエアは配管の材質によって、帯電量や極性が変わってきます。ここではシリコーンとアクリルを紹介していますが、別の素材も試しています。その結果、+側からアクリル、ナイロン、ポリエステル、PVC、テフロンがより-という順番になりました。 |
 実験ムービー シリコンチューブから出る空気の帯電と除去 実験ムービー シリコンチューブから出る空気の帯電と除去
|
 実験ムービー アクリルパイプから出るエアの帯電と除去 実験ムービー アクリルパイプから出るエアの帯電と除去
|
 静電気対策のポイント 静電気対策のポイント
空気も静電気を帯びます。エアブローの他に、真夏の冷房や冬の暖房などエアコンの風が静電気の発生源になることがあります。 |
 |
| 【実験④】 アルミ箔のブランコ |
| 絶縁物の上にのっている金属は何度も放電してしまうことがあります。静電気吸着とは関係ありませんが、放電は装置のノイズとなり、ときには誤動作の原因にもなるので注意が必要です。 |
 実験ムービー アルミ箔のブランコ 実験ムービー アルミ箔のブランコ
|
 静電気対策のポイント 静電気対策のポイント
なぜ、アルミ箔がくっついたり、離れたりするのか、上の資料で説明します。初め、アルミ缶はプラスに帯電しています。このとき、アルミ箔中の自由電子がアルミ缶の方へ引き寄せられくっつこうとします。しかし、一度くっつくと電子の移動が起こり、アルミ箔はプラスに帯電してしまい、反発するのです。さらにアースにつなぐとアルミ箔は初期状態に戻り、再び、アルミ缶にくっつこうとします。
|
 |
| 【実験⑤】 帯電列・まだら帯電 |
 |
【実験の準備】
- アクリル板・ポリエチレン袋・Jチェッカー(テフロン製) ※表面抵抗値の高い異なる素材であればOK
- 表面電位計
【実験方法】
それぞれの素材を擦り合わせ静電気を起こして、表面電位計にて表面の帯電圧を測定する。 |
 |
まず、アクリル板の保護紙をはがすとそれだけで静電気が発生します。
測定すると+8.2KVでした。
保護紙(内側に何らかのフィルムが貼ってあった)とアクリル板の関係でアクリル板が+に帯電したと考えられます。 |
 |
 アクリル板 vs ポリエチレン袋 アクリル板 vs ポリエチレン袋
次にポリエチレン袋(ホームセンターで買い物をして入手)でアクリル板を擦ってみました。アクリル板は前回同様、+に帯電しています。 |
 |
このとき、ポリエチレンの袋は-5.4KVに帯電していました。
下の帯電列表で確認すると(+)アクリル板<ポリエチレン(-)なので、表の通り。 |
 |
 アクリル板 vs テフロンシート アクリル板 vs テフロンシート
次に素材の組合せを代え、アクリル板 VS Jチェッカー(テフロン)を擦ります。
この場合はアクリル板(+)、テフロン(-)に帯電しています。 |
 |
テフロンは帯電列ではもっともマイナスよりに位置しており、静電気も発生しやすい物質です。この場合は-4.4KV帯電していました。 |
 |
 テフロンシート vs ポリエチレン袋 テフロンシート vs ポリエチレン袋
最後にJチェッカーをポリエチレン袋で擦ります。すると、もっともマイナスに帯電するテフロンはやはりマイナスに帯電しましたが・・ |
 |
帯電列ではテフロンよりも+側に位置するポリエチレンは先ほどとは逆に、+側に1.04KV帯電していました。 |
 実験ムービー ※写真をクリックするとムービーが始まります。 実験ムービー ※写真をクリックするとムービーが始まります。 |
 |
そして、ポリエチレン袋を広げてみると全体は-側ですが、テフロンで擦ったところだけは+側に傾いていることが分かります。
つまり、同じワークの中に極性が違う帯電状態が混在しているのです。この状態をまだら帯電といいます。 |
 静電気対策のポイント 静電気対策のポイント
帯電列は下表のようにまとめられ、離れているほど帯電しやすく、+~-の順に帯電するといわれていますが、実際にやってみるとなかなか再現できません。総じて樹脂は-に帯電しやすく、帯電列で近いものでも強く帯電するようです。
また、対象物が絶縁物であれば、内部で電気は流れないので静電気はまだら模様に帯電してしまいます。そのとき、ひとつの対象物に+もーも同時にありうるのが特徴です。
|
 |
| 【実験⑥】 静電気吸着と帯電圧 |

ポラリオン
クリーンルームライト |
【実験の準備】
- ポラリオン クリーンルーム ライト
- チャージプレートモニター
【実験方法】
チャージプレートモニター上を帯電させ、通過するゴミ・ホコリが静電気によって吸着する(または弾き飛ばされる)様子をポラリオン クリーンルーム ライトを使って観察します。 |
 実験ムービー ※写真をクリックするとムービーが始まります。 実験ムービー ※写真をクリックするとムービーが始まります。 |
 |
帯電圧が1KVの場合はさほど変化はなく、ゴミ・ホコリは気流に沿って流れていきます。 |
 実験ムービー ※写真をクリックするとムービーが始まります。 実験ムービー ※写真をクリックするとムービーが始まります。 |

|
帯電圧が5KV以上になると気流に関係なく、プレートに飛び込む、あるいは飛び出すゴミ・ホコリが多く観察されるようになります。ビデオで撮影されているゴミの大きさはほとんど目に見える大きさのゴミです。さらに小さなクリーンルームで対象となるサイズのゴミはこれより低い電圧で同様の現象が起こると予想されます。 |
 静電気対策のポイント 静電気対策のポイント
静電気でゴミがどのように付着するのか目視確認できれば、対策も取り易くなります。ポラリオンライトとの組合せで「見える化」が容易になります。 |
 |